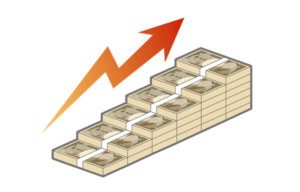時間単位年休の管理方法について

労働基準法39条では、労働者にとって健康で、ゆとりのある生活の実現のため、会社は6か月以上継続勤務し、かつ8割以上出勤した社員に対して一定日数の年次有給休暇を与えなければならないと定めていますが、日本の会社、特に中小企業では、この年次有給休暇が取得の促進が図られていないのが現状です。このような問題を解消し、年次有給休暇の取得の促進を図るために活用できる制度として、労働基準法では労使協定(※)の締結により、1時間単位で年次有給休暇を取得することができる制度(以下「時間単位年休」といいます。)が定められています。

この時間単位年休ですが、取得単位が細かくなりますので、年次有給休暇の残り日数(残り時間)の管理や繰り越し管理が非常に煩雑になることもあり、実際に制度を導入している企業割合は約2割に留まっており、制度の導入は十分に進んでいないのが現状です。今回のブログでは、時間単位年休の制度概要や、時間単位年休の管理方法について詳しく解説していきます。
(※)労使協定は、使用者と労働者代表の間で取り交わす書面契約のことをいいます。
目次
時間単位年休の概要

「時間単位年休」とは、1時間を単位として年次有給休暇を取得することを認める制度になります。1日の所定労働時間(就業規則や雇用契約書で定めた1日の基本的な労働時間)が8時間の労働者であれば、年次有給休暇1日分を8分割して取得することが可能になります。最小の取得単位は1時間となりますので、3時間などと時間を指定して取得することも可能になります。ただし、30分単位など、1時間に満たない単位で取得することはできません。時間単位年休制度についてポイントなる点は次の通りになります。
労使協定の締結と就業規則への記載
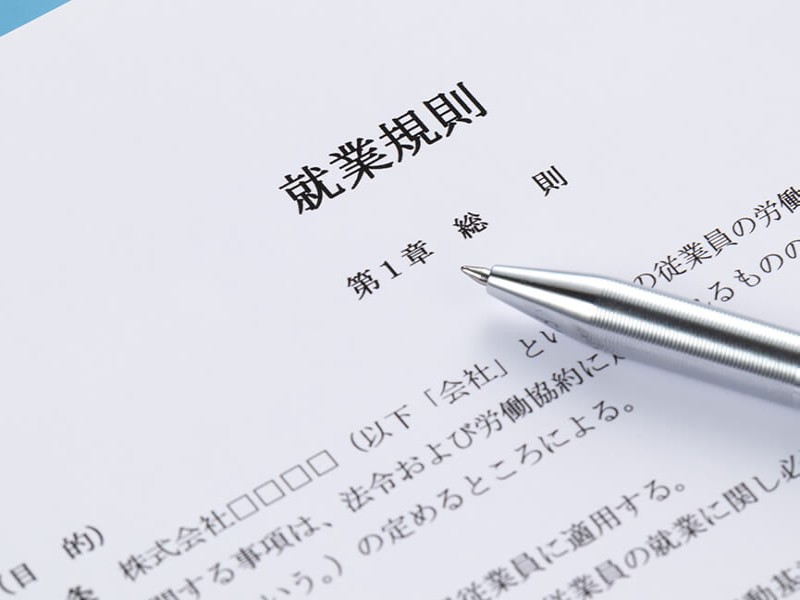
時間単位年休を制度として導入するためには、時間単位年休に関する労使協定を締結し、時間単位年休に関して就業規則に規定し、労働者へ周知することが必須になります。時間単位年休に関する労使協定について、記載内容は次のとおり法律で定められています(※労働基準監督署への届出義務はありません)。
(1)時間単位年休を取得することができる労働者の範囲
➡時間単位年休を取得することができる労働者の範囲については会社の判断に委ねられていますが、通常の年次有給休暇と同様、時間単位年休の利用目的を制限することはできません。
(2)時間単位年休として取得できる日数(年間上限5日まで)
➡時間単位年休を取得することができる日数の上限は年間5日間とされているため、労使協定においても、5日間を上限として日数を定める必要があります。
(3)1日分の年次有給休暇に相当する時間数
➡労使協定において、1日分の年次有給休暇が、何時間分の時間単位年休に相当するかを定めておく必要があります。なお、日によって所定労働時間数が異なる場合(シフト制勤務の場合等)には、1年間における1日の平均所定労働時間数を算出し、その時間数を1日分の時間単位年休の時間数とします。
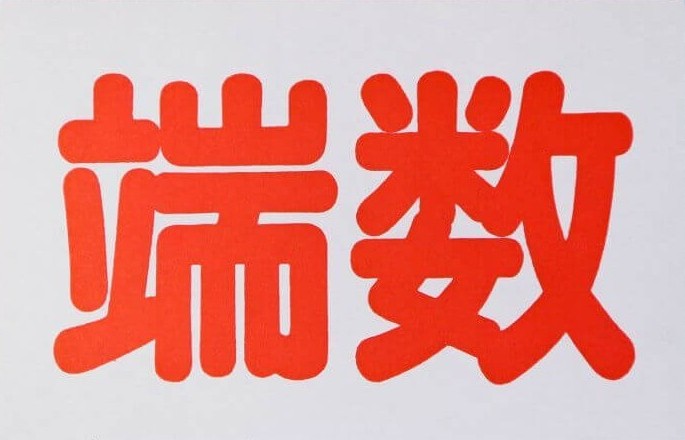
労働者の所定労働時間に1時間未満の時間がある場合には、1時間未満の端数を1時間に切り上げて1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するか判断する必要があります。例えば、1日の所定労働時間が6時間30分の労働者の場合、1日の年次有給休暇は、7時間(端数切上げ)分の時間単位年休に相当することになります。
(4)1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
➡1時間以外の時間を取得単位とする場合には、労使協定にその旨記載する必要があります。ただし、前述のとおり30分単位など1時間に満たない単位で時間単位年休を取得することはできません。

時間単位年休を取得した場合の賃金は、1日単位で年次有給休暇を取得した場合に通常支払われる賃金を計算した後、その賃金をその日の所定労働時間で除して算出することになります。
時間単位年休の時季変更権について

年次有給休暇を取得することは労働者の権利になります。年次有給休暇は、原則として労働者が請求する時季に与えることとされています(労働者の時季指定権)。ただし、労働者が請求する日に年次有給休暇を取得させることにより、事業の正常な運営が妨げられる場合、会社(使用者)が、年次有給休暇取得日時を他の時季へ変更することが認められています(使用者の時季変更権)。


時間単位年休も、1日単位の年次有給休暇と同じく、会社(使用者)に時季変更権が認められます。ただし、労働者が時間単位年休の取得を申請したにも関わらず、会社がこれを1日単位に変更するよう命じることや、逆に、1日単位の有給休暇の取得を申請したにも関わらず、これを時間単位年休に変更するよう命じることは、時季変更権には該当せず、法律上認められませんので注意が必要です。
時間単位年休の管理方法

時間単位年休制度ですが、働く側にとっては利便性が高く、厚生労働省の統計調査によれば、実際に50%以上の労働者が時間単位年休の導入を希望しています。にも関わらず、時間単位年休制度の導入割合が20%に留まっているのは、時間単位年休の残日数管理や繰越日数の管理が非常に煩雑になることが要因として考えられます。時間単位年休を導入した場合の注意点、管理方法について詳しく見ていきましょう。
使用者による年5日の時季指定との関係

10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうち5日については毎年時季を指定して与えなければならないとされています。この5日ですが、労働者自ら時季指定して取得した日数については、付与義務のある5日から控除することが認められていますが、時間単位年休を取得した場合については、付与義務のある5日から控除することができません。

➡例えば、10日の年次有給休暇が付与された場合で、1日の所定労働時間が8時間の労働者が40時間の時間単位年休を取得した場合でも、使用者による時季指定は1日も行われていないことになります。
時間単位年休と業務中の中抜けについて

時間単位年休取得による中抜けを認めると、業務調整や勤怠管理が煩雑になり、業務効率も悪くなる等の理由から、時間単位年休取得による中抜けは認めたくないというご意見をいただくことがありますが、「所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限することは認められない(平成21年5月29日基発0529001号)」とされていますので、労働者から請求があった場合には、事業の正常な運営に支障を来す事情がない限り、労働者が指定する通り時間単位年休を与え、中抜けを認める必要があります。

➡「時間単位年休を取得しての中抜けを認めない」という内容の労使協定を締結したとしても、労働者から請求があった場合には、事業の正常な運営に支障を来す事情がない限り、労働者が指定する通り時間単位年休を与え、中抜けを認める必要があります。
残り日数(残り時間数)の管理方法
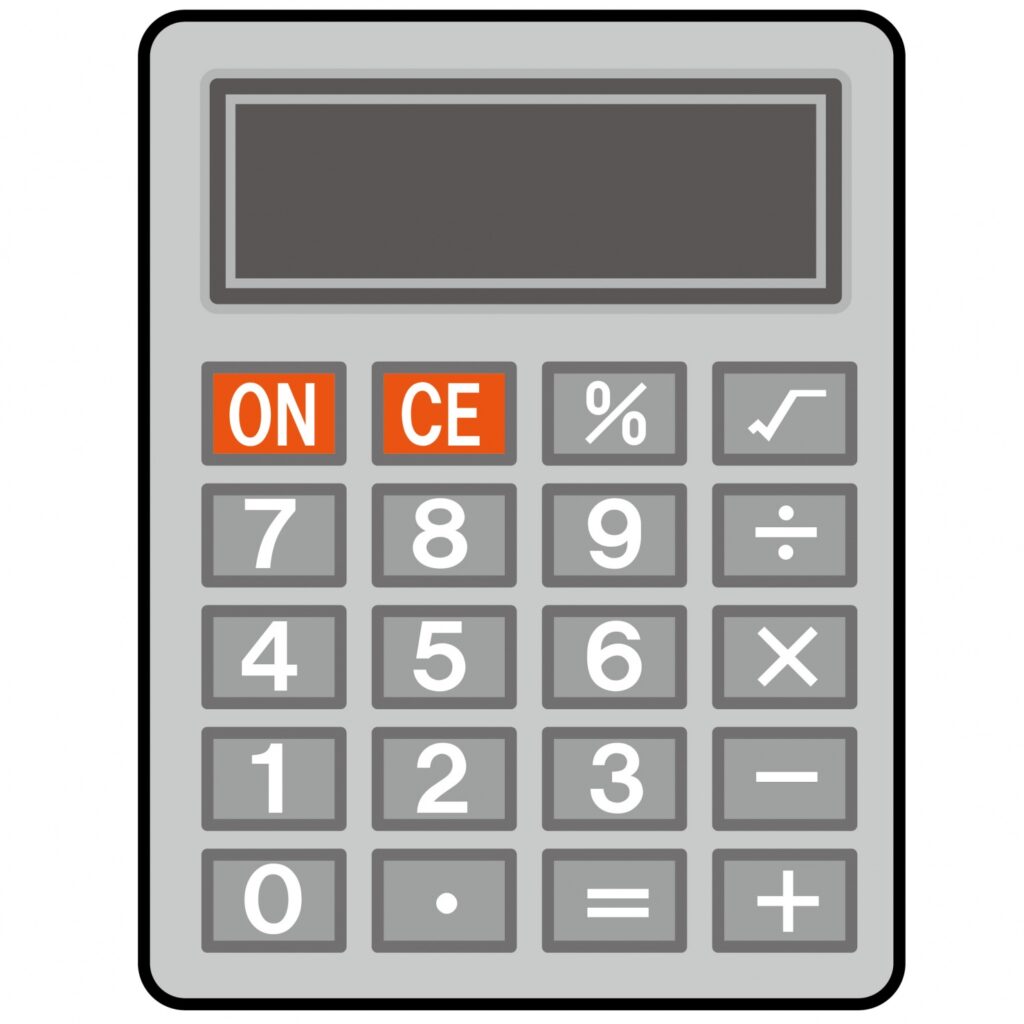
時間単位年休を導入した場合、残り日数や残り時間数の管理方法として、① 【日数】+【時間数】で管理する方法、② 【すべて時間数】で管理する方法が考えられます。どちらの管理方法でも法律上問題になることはありませんが、原則は①の【日数】+【時間数】で管理すべきです。その理由について具体例を挙げて見ていきましょう。

| 具体例 | |
| (1)年次有給休暇付与日数 | 10日 (時間単位年休5日) |
| (2)1日の所定労働時間 | 8時間 |
| (3)時間単位年休の取得時間 | 5時間 |

| 管理方法 | |
| ① 【日数】+【時間数】で管理する方法(※原則) | ➡年次有給休暇の残り日数(残り時間数)は9日と3時間、そのうち時間単位年休の残り日数(残り時間数)は4日と3時間となります。 |
| ② 【すべて時間数】で管理する方法 | ➡時間単位年休の総枠40時間(8時間×5日)のうち5時間を時間単位年休として取得した場合、時間単位年休の残り時間数は35時間となります。 |
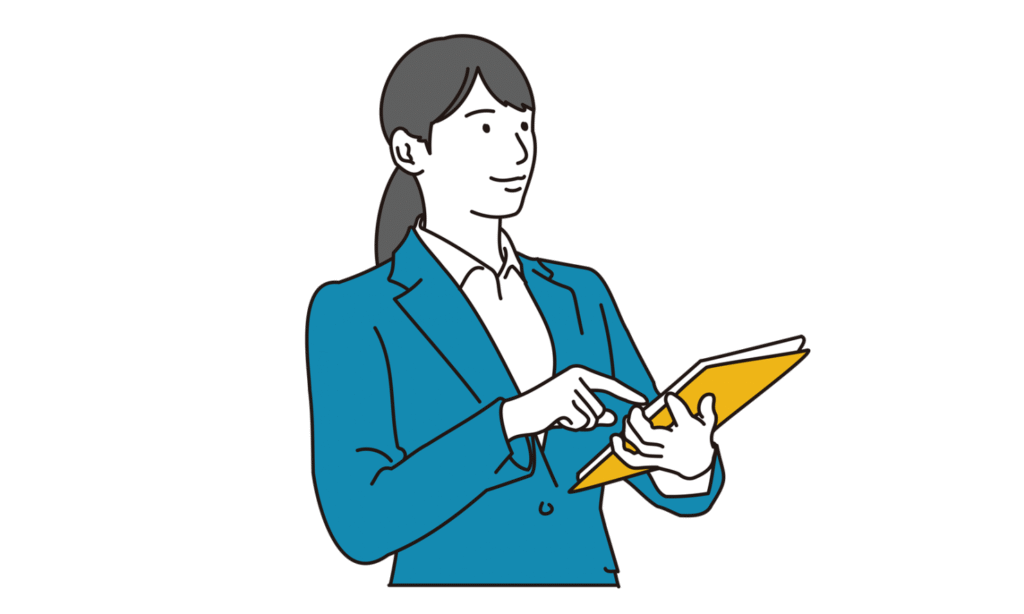
時間単位年休を導入した場合でも、年次有給休暇を時間単位で取得するか、1日単位で取得するかは労働者自らの意思で判断することになります。時間単位年休の残り日数や残り時間数を【すべて時間数】で管理した場合、日単位で取得できる日数を労働者が把握しづらくなります。また、時間単位年休について翌年度への繰り越しを正しく行うためにも、残り日数や残り時間数については、原則の【日数】+【時間数】で管理するようにしましょう。
時間単位年休の翌年度への繰り越しについて

年次有給休暇は時効により、付与日(基準日)から2年で消滅します。 付与日(基準日)から1年間の間に取得できなかった年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越されます。時間単位年休についても、付与日(基準日)から1年間の間に取得できなかった部分について、翌年度に繰り越されることになりますが、時間単位年休については、前年度から繰り越された日数(時間数)がある場合、その日数(時間数)を含め5日(時間単位年休を取得できる1年度の上限日数)の範囲内とする必要があります。

➡つまり、時間単位年休を翌年度に繰り越した場合、5日(時間単位年休を取得できる1年度の上限日数)+繰り越し日数(時間数)となるのではない点に注意が必要です!

➡時間単位年休の翌年度への繰り越しについて具体例を挙げて見てみましょう。なお、今回の具体例については、使用者による年5日の時季指定については考慮しないものとします。
| 具体例(その1) | |
| (1)年次有給休暇付与日数 | 10日 (時間単位年休5日) |
| (2)1日の所定労働時間 | 8時間 |
| (3)時間単位年休の取得時間 | 年度内に21時間取得 |
| (4)時間単位年休の管理方法 | 【日数】+【時間数】で管理 |


➡上記の具体例の場合、時間単位年休を【日数】+【時間数】で管理していますので、翌年度に繰り越される年次有給休暇の残り日数(残り時間数)は7日+3時間となります。言い換えると、時間単位年休の取得時間が8時間(1日の所定労働時間)に達したときは、1日単位に繰り上げ、通常の年次有給休暇を取得したものとして取り扱い、8時間未満の時間数のみ時間単位年休として翌年度に繰り越すことになります。
| 具体例(その2) | |
| (1)前年度からの年次有給休暇の繰り越し日数 | 7日+3時間 |
| (2)当年度の年次有給休暇付与日数 | 11日 |
| (3)当年度の年次有給休暇合計日数 | 18日+3時間 |


➡1年度のうち、時間単位年休として取得できる日数の上限は5日になりますが、前年度からの繰り越し分がある場合、その時間数を含め5日以内とする必要がありますので、上記具体例(その2)の場合、当年度に取得できる時間単位年休5日の内訳は、【前年度からの繰り越し分3時間】+【当年度に新たに付与された年次有給休暇11日のうち、37時間(4日+5時間)】ということになります。
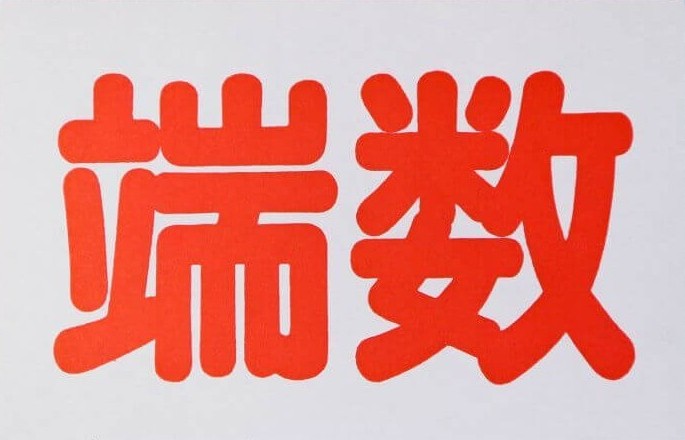
具体例(その2)のケースでは、前年度から3時間分の時間単位年休が繰り越された結果、当年度に付与される年次有給休暇11日のうち、3時間の端数が生じることになります。前にご説明した通り、1年度に取得できる時間単位年休の上限は5日と定められていますので、この3時間の端数について、当年度内に時間単位年休として付与することができません。


➡時間単位年休を翌年度へ繰り越した場合の1日未満の端数の取り扱いについては、労使協定や就業規則で定める必要がありますが、次のような取り扱いが認められています。
| ① 翌年度への繰り越しを認める | ➡1年度に取得できる時間単位年休の上限は5日となるため、法律上取得することができない時間単位年休の端数については、2年の時効で消滅させるのではなく、翌年度の年次有給休暇の付与時に繰り越す。 |
| ② 1日単位に切り上げる | ➡時間単位年休を繰り越した結果、当年度に時間単位年休として取得できない端数が生じた場合、それを1日に切り上げ、年次有給休暇1日分として付与する。 |

①、②いずれの取り扱いも、労働者にとって不利になるものではないので、どちらの取り扱いとするかについては、時間単位年休導入時、労使の話し合いで決めることになります。ただし。②の取り扱いについては、当年度に時間単位年休として取得できない端数が生じた場合で、かつ、その端数を翌年度に繰り越すことができない場合(退職時等)のみ適用するのが実務上一般的です。

時間単位年休制度は、働く側にとって利便性が高く、育児や介護と仕事の両立支援にも有効な制度ですので、働く側からのニーズは高い制度になりますが、制度導入にともない、会社の勤怠管理や給与計算は極めて煩雑になりますので、制度導入が十分に進んでいないのが現状です。

一方、深刻な人材採用難という環境の中、働きやすさ向上を通じて採用競争力を高めたいとう会社も増加していますので、今後は時間単位年休制度の導入増加が予想されますし、また、時間単位年休制度に関するルールについても、今後大きく改正されていくことが予想されます。時間単位年休の制度概要や導入にあたり、ご不明な点があればぜひ当事務所までお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。
TEL:045-262-0214
受付時間:9:00-18:00(土曜・日曜・祝日除く)